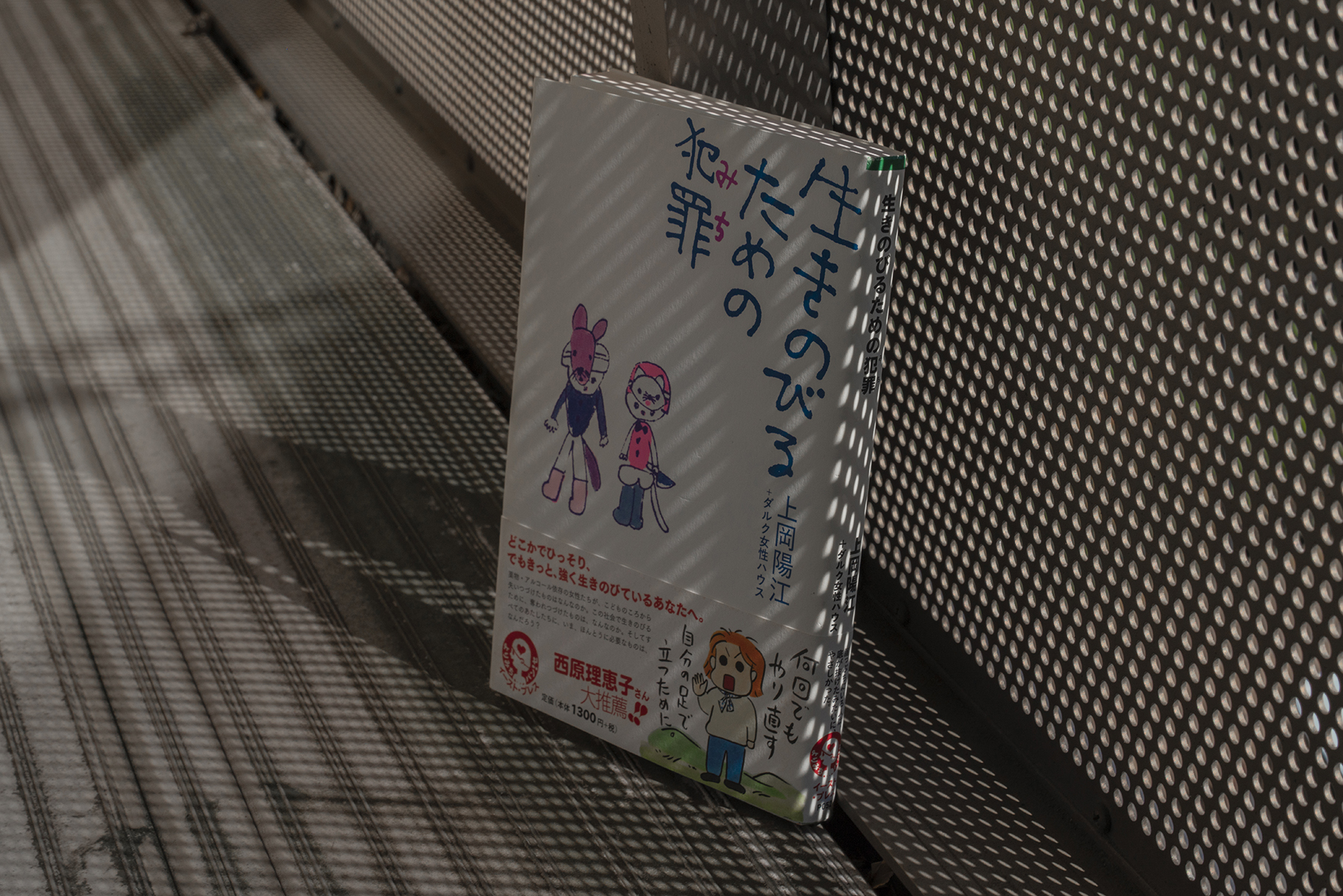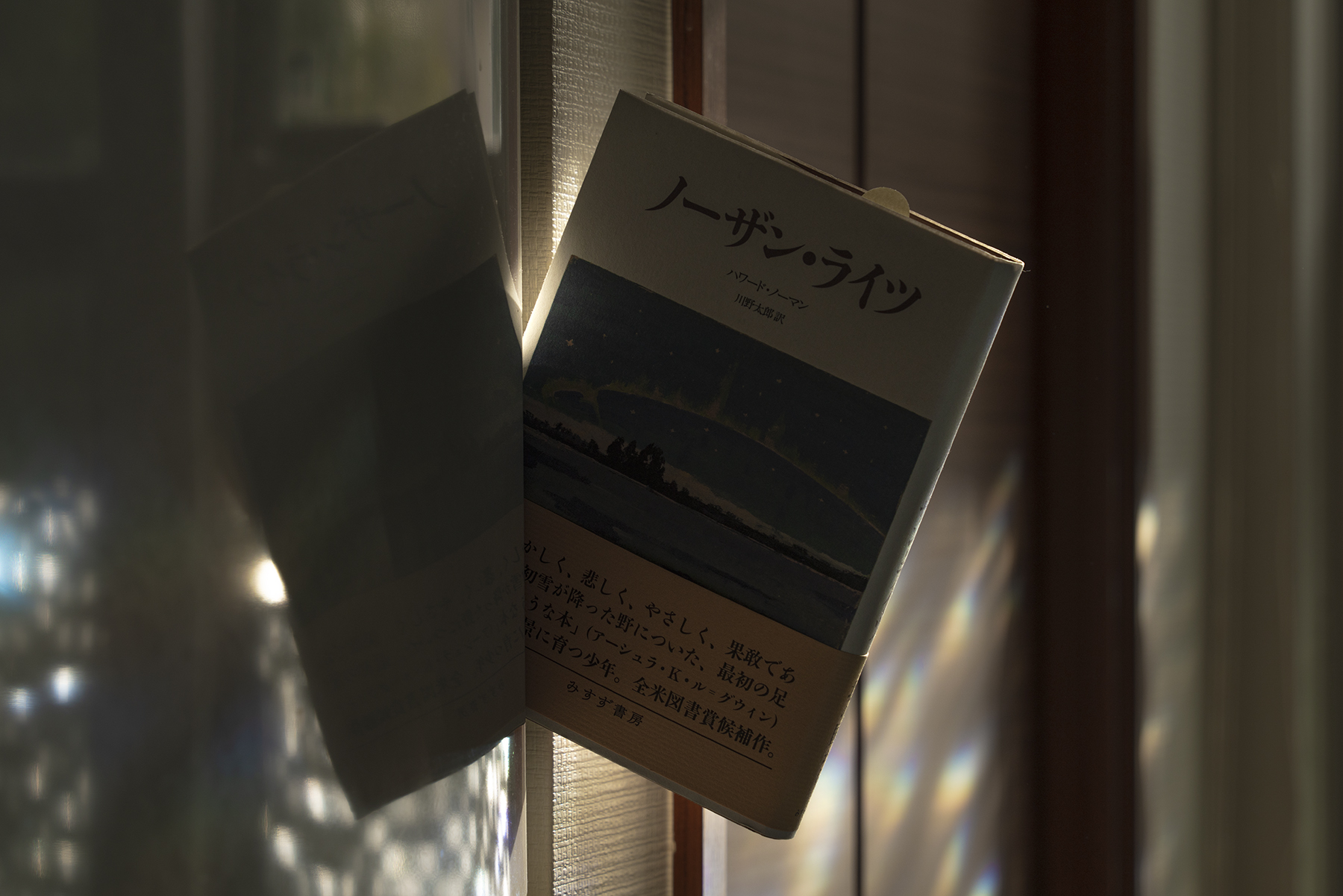辺境のブックス・レビュー


オルタナティブに生きる人
21世紀の「石井先生」はどこにいるのか?『偶然の装丁家』|松村圭一郎
2021.11.05
/ Posted on
2021.11.05
- / 編集:
- 平岩 壮悟
- / 撮影:
- 村田 啓
まじめに学校に通い、がんばって勉強して、いい大学に入り、安定した職につく。そういう人生の歩み方しか、まわりの大人たちは教えてくれなかった。そんな人もいるかもしれない。「オルタナティブを生きる人の本」で、すぐ思い浮かんだのが、画家であり装丁家である矢萩多聞さんの『偶然の装丁家』だ。シリーズ「就職しないで生きるには」の一冊として書かれた本書には、誰もが信じこまされてきた生き方の固定観念をぐらぐらと揺さぶられる。
矢萩さんは、小学校4年生で不登校になった。学校が楽しくなかったわけではない。決まったことをみんなと同じようにやらないと怒る先生と「そりがあわなかった」。遅刻、忘れ物、宿題をやらない。そんなマイペースな矢萩さんに、先生は言った。「勉強ができず、みんなと協調できない子は、大学に行けず、社会に出ても仕事がなくて、乞食になるしかないのよ」。
4年生の3学期、校長先生が家に来て、好きな友だちと同じクラスにするし、熱心な先生を担任にするので学校に来てほしい、と言われた。それで矢萩さんは5年生から学校に通いはじめる。担任となった「石井先生」は、まさに規格外の先生だった。遅刻してこそこそと教室に入ると、「もっと堂々とはいってきなさい」と言われる。国語の授業では、ほぼ1学期、宮沢賢治の「やまなし」しかやらない。社会科の授業も超スローペースで、「卑弥呼はどんな果物が好きだったか」というトピックだけで何時間も話し込み、生徒たちに火がつくと簡単に時間割が変更され、午前中ずっと社会科だけの授業になった。
「最高に楽しかった2年間」を終えて、中学校に入ると、またどんよりした日々に戻った。矢萩さんは、中学1年の終わりから学校に行くのをやめ、5年生のときに家族と旅行したインドで暮らしたいという思いを募らせる。そして14歳から19歳までの5年間、ビザが切れると日本に帰国しつつ、インドでの生活を続けた。町の地図をつくる。インド映画にはまる。屋上に寝転んで空を眺める。絵を描き、詩を書き、本を読む……。とくに何かをするわけでもない自由で静かな一日は、それでもとても「濃密な時間」だった。
ときどき「うちの子もインドに行けば、多聞さんみたいに才能が花開くんでしょうか」と相談される。でも矢萩さんは「インドに行って人生観が変わったり、才能が開いたりするなんてこと、まず、ないですよ!」と答える。「親御さんのそういう考え方をやめてあげてください。才能とか個性とか、子どもには重荷しかならないので……」と言っても、なかなか伝わらない。「その時どきに出会った人たち、物事の流れのなかで、おぼろげに自分のカタチが浮かびあがる、そちらのほうが自然じゃないか」。矢萩さんはそうつづる。
小さいときから矢萩さんは絵を描くのが好きだった。でも学校の図工・美術の成績はずっと5段階評価で最低の「1」。学校では課題ごとに提出日が決まっている。じっくり時間をかけたい矢萩さんはいつも提出日に間に合わず、「未提出」となった。「石井先生」だけは、どれだけ時間をかけてもいいと許してくれたので、学期をまたいで何枚も絵を完成させた。でも中学に入ると、また「1」になった。美術の先生はたずねてもいないのに、未完成の絵をみて、あれこれアドバイスしてくる。「言われれば言われるほど、絵を描く気は失せていく」。唯一の楽しみだった美術の授業が、とても気の重い時間になった。
『偶然の装丁家』を読むと、自分の生き方を問い返される。1年浪人したし、大学を休学してエチオピアに行ったり、大学院生時代が長くて最初に就職したのも30歳の年だったりもするが、私の歩んだ人生は(結果的に現時点では)高学歴の安定コースの部類なのだろう。でもこの本は他人事としては読めない。おそらく矢萩さんが画家や装丁家として「自分のカタチが浮かびあがる」までになれたのは、「石井先生」のようにその生き方を支える大人がそばにいたからだ。そんなちゃんとはみだした大人として、若い人たちに向き合えているのか。矢萩さんのようには生きられなかった自分なりに、みずからを問われるのだ。

『偶然の装丁家』(矢萩多聞著/晶文社)
1975年熊本生まれ。岡山大学文学部准教授。専門は文化人類学。所有と分配、海外出稼ぎ、市場と国家の関係などについて研究。著書に『うしろめたさの人類学』(ミシマ社、第72回毎日出版文化賞特別賞)、『はみだしの人類学』(NHK出版)、『これからの大学』(春秋社)、『くらしのアナキズム』(ミシマ社)など、共編著に『文化人類学の思考法』(世界思想社)、『働くことの人類学』(黒鳥社)。


バックナンバー
辺境のブックス・レビュー
一人ひとり異なる「自由」を拓くために
一冊の本から思想的辺境に立つ