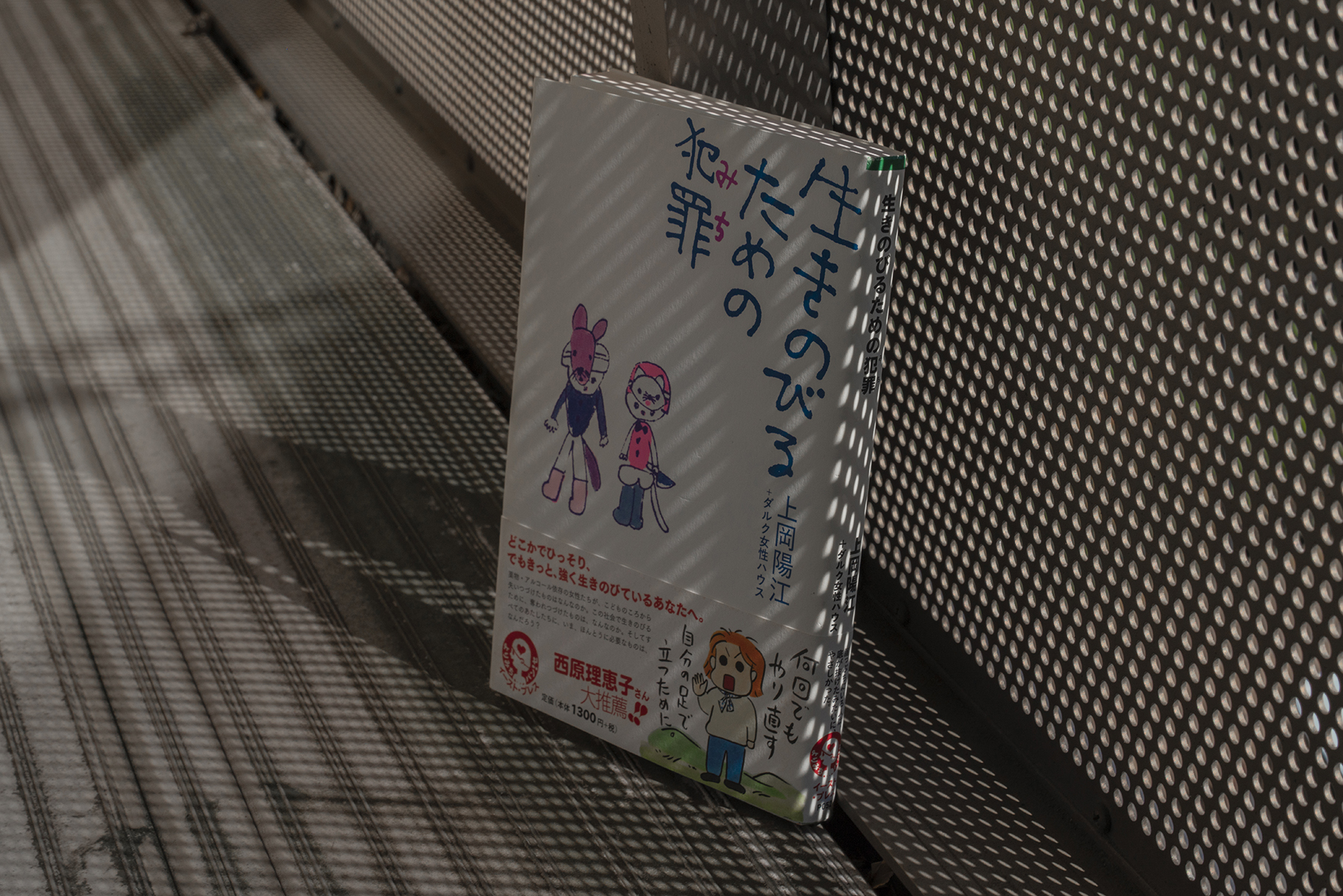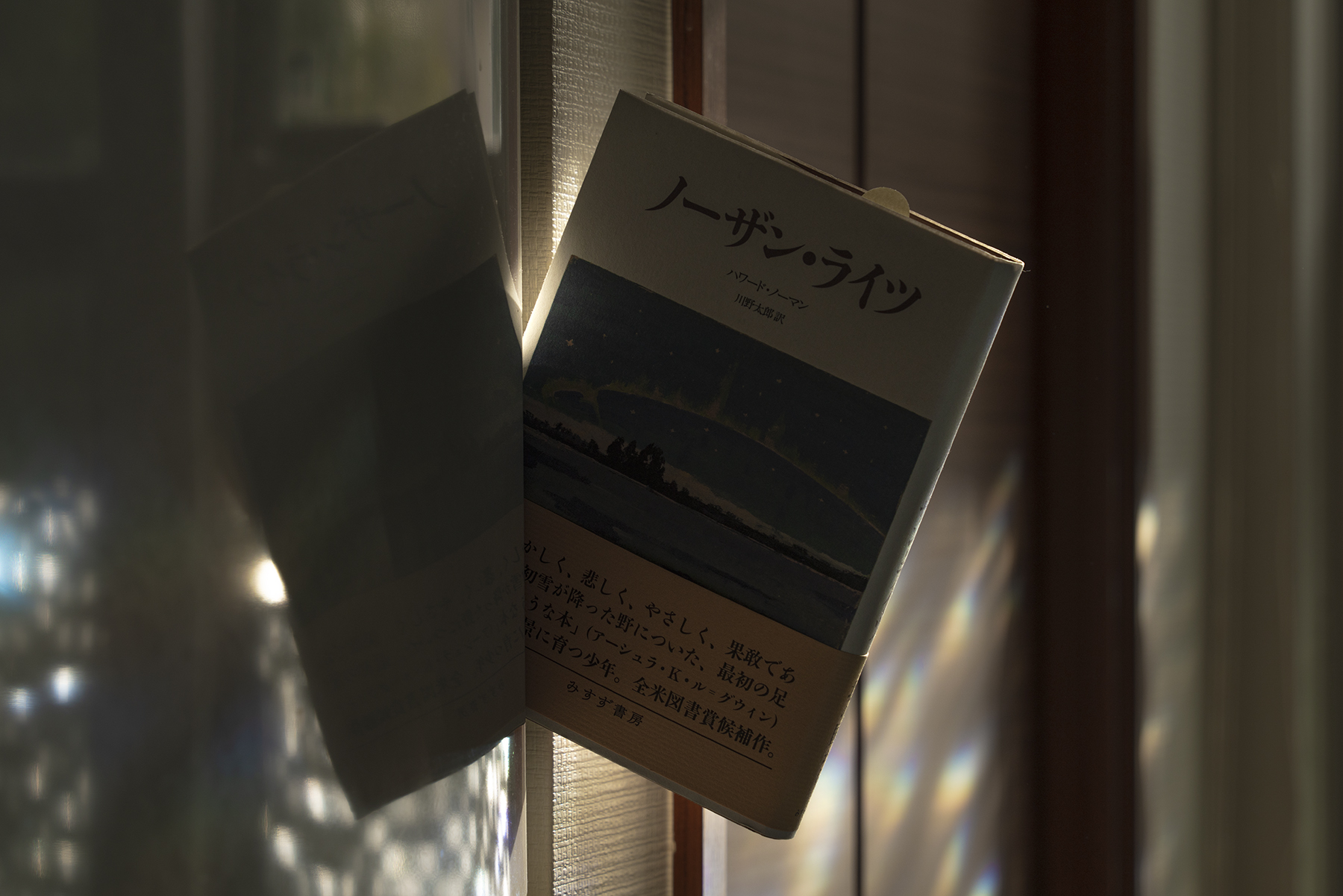辺境のブックス・レビュー


オルタナティブに生きる人
「弱い生」に宿る革命可能性ーー『金子文子 わたしはわたし自身を生きる』|高島鈴
2021.11.12
/ Posted on
2021.11.12
- / 編集:
- 平岩 壮悟
- / 撮影:
- 村田 啓
文子はかっこよくて羨ましい。でも文子みたいになりたいと言ってしまうと負けた気になるから、絶対に言わない。
金子文子の手記「何が私をこうさせたか」に獄中歌集と調書を加えて編纂された『金子文子 わたしはわたし自身を生きる』(鈴木裕子編、梨の木舎)について、私はすでに一度書評をしたことがある。冒頭の文章はその末尾を抜粋したものだ。23歳、つまり文子の享年と同じ歳の頃であった。
あれからすでに3度、文子より長く生きてしまった、と思いながら誕生日を数えている。公権力に対する敵意、天皇制に対する殺意を最期まで研磨し続けた若い人は、永遠に若いまま私から遠ざかる。
金子文子は20世紀初頭を生きた活動家だ。無戸籍児として生まれ、壮絶な虐待経験のなかで育った。やがて東京へ出て苦学生となると、虚無主義者(ニヒリスト)として社会運動の波に身を投じる。のちに公私にまたがる伴侶となる朝鮮半島出身の虚無主義者・朴烈と出会い、関東大震災の頃、皇太子暗殺計画を立てた疑いで逮捕された。この皇太子暗殺計画は実際のところほとんど実現可能性の低いものであり、文子に関して言えば計画を知らされてすらいなかったが、政府は関東大震災に際して起きた朝鮮人虐殺を正当化するために、ふたりを吊るすと決めたのだ。文子は転向すれば罪を免れると理解しながら、韓服をまとって大審院へ出廷し、死刑判決に万歳で応じ、恩赦の書面を破り捨て、獄中で自ら命を絶った。奪われたものを奪い返すための闘争に駆られ続けた人だった。
先に文子は虚無主義であると述べたが、その思想には変遷がある。文子はもともとアナキストの志向する権力なき社会の建設を「幸福な考え方」と呼んで激しく退け、「自然を呪い、社会を呪い、生物を呪って、私はすべての物を破壊して自分は死のうと思います」と述べてきたのであるが、死の前年に当たる1925年、生を肯定する、とその意志を翻すのだ。文献上把握しうる文子の最期の自己定義は、「個人主義的無政府主義者」であった。
文子の言う「生の肯定」は、単純な生命維持の肯定ではない。文子は「生きる」ことをその主体性の発揮と位置づけ、その結果として肉体が破滅しようと、それは生の肯定になるのだと主張している。
私はこの考えすべてに賛同はしない。自己の意志を奪われてなお生き延びる道が、のちの抵抗に連続する可能性を、私は絶対に棄てるべきではないと思う。奪われてなお生きる者の弱い生にこそ、革命可能性が潜む。
ただ一方で、万物の絶滅を望んだ文子が、己の破滅を死への接近ではなく何よりも強い生として捉え直した点に、どうしても身の内が燃えるような感覚を覚える。結果が受け止めがたくとも、この思想的転回は文子の見た希望だったのだ。肯定しきれない「「極端」」な革命思想を前にして、私はうなずけないがゆえに、文子という揺れる人の存在そのものには絶対的にうなずきたいのだと、文子の年を通り越した今、強烈に思う。
あなたはそういうふうにしか生きられなかったし、その言葉はすべてが妥当だった。あなたから引き継げるものは、引き継げるかぎり引き継がねばならない。
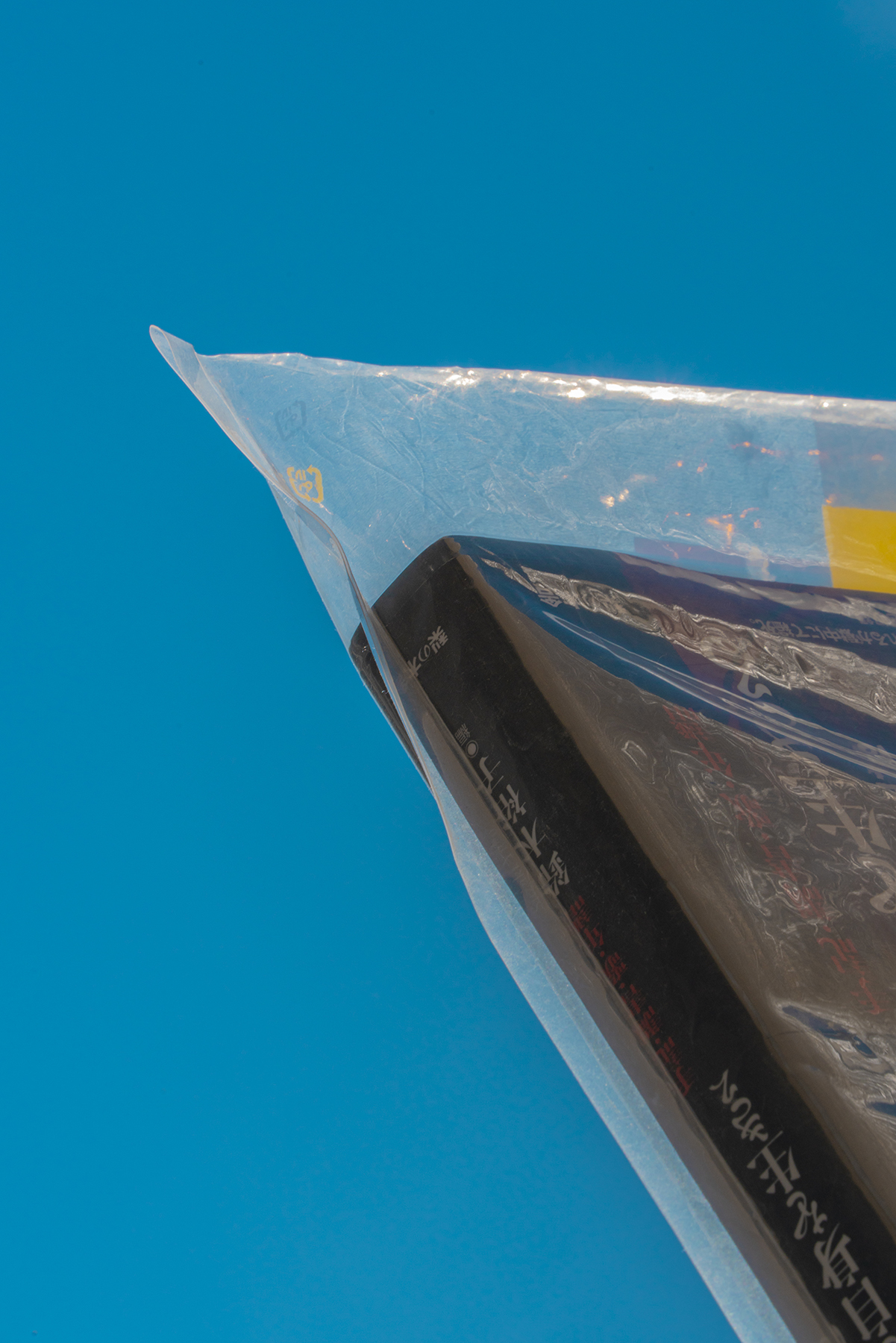
『金子文子 わたしはわたし自身を生きる』(鈴木裕子編/梨の木舎)
高島鈴(たかしま・りん)
1995年、東京都生まれ。ライター。連載にエッセイ「There are many many alternatives. 道なら腐るほどある」(ele-king)、少年漫画批評「くたばれ、本能。ようこそ、連帯。」(Webちくま)、エッセイ「シスター、狂っているのか?」(新書館『シモーヌ』)がある。そのほか、『文藝』(河出書房新社)、『ユリイカ』『現代思想』(青土社)、『週刊文春』(文藝春秋)、山下壮起・二木信編著『ヒップホップ・アナムネーシス』(新教出版社)などに寄稿。