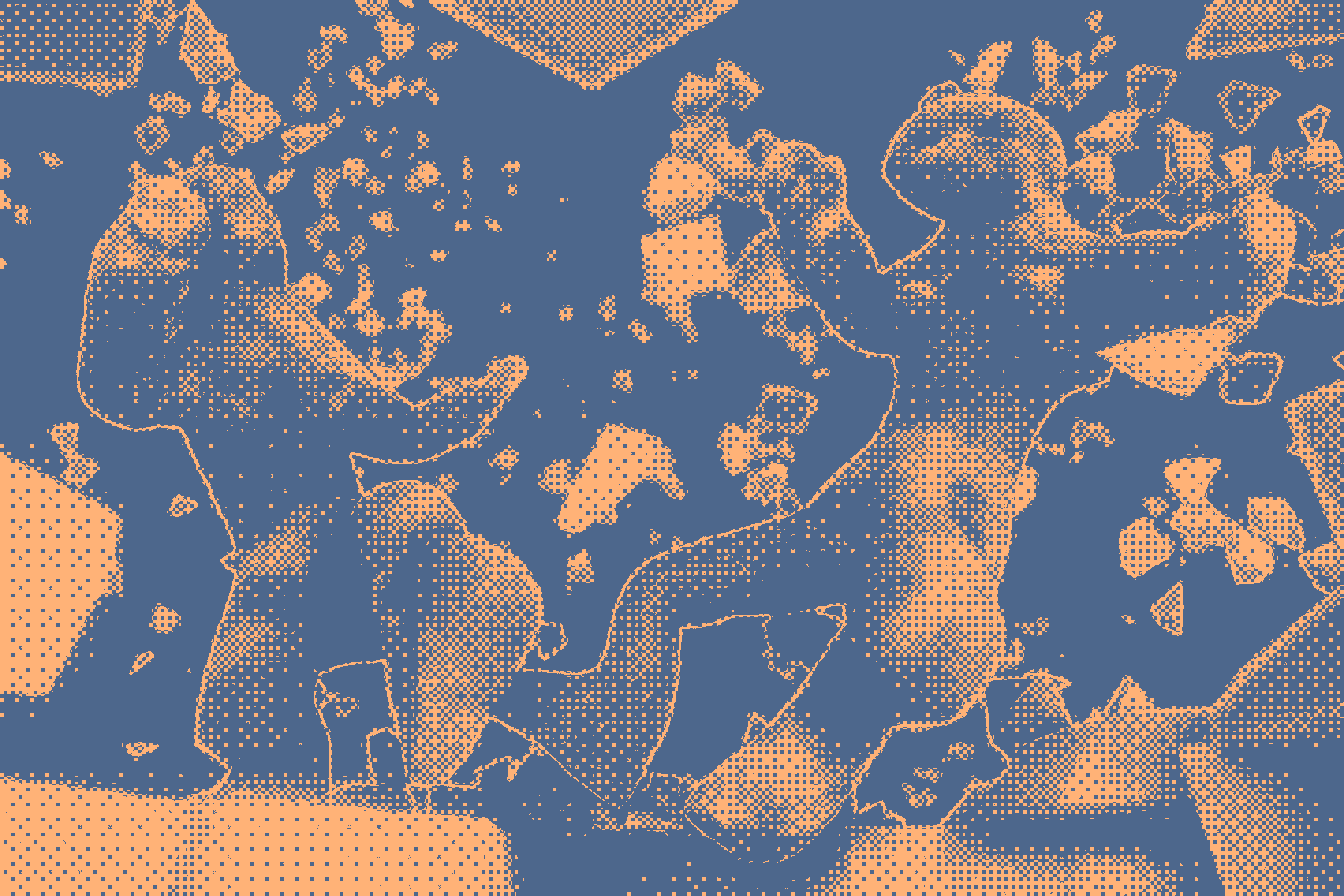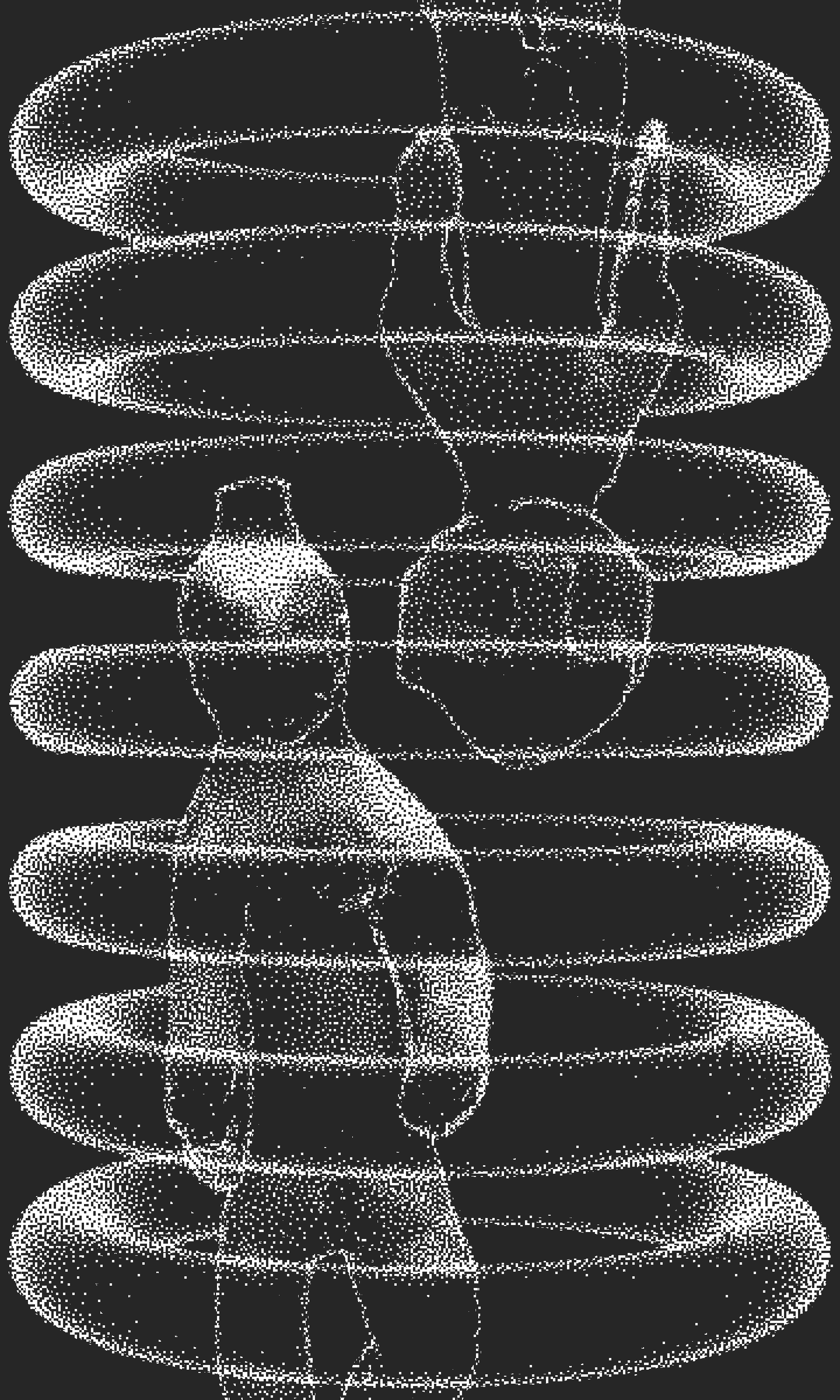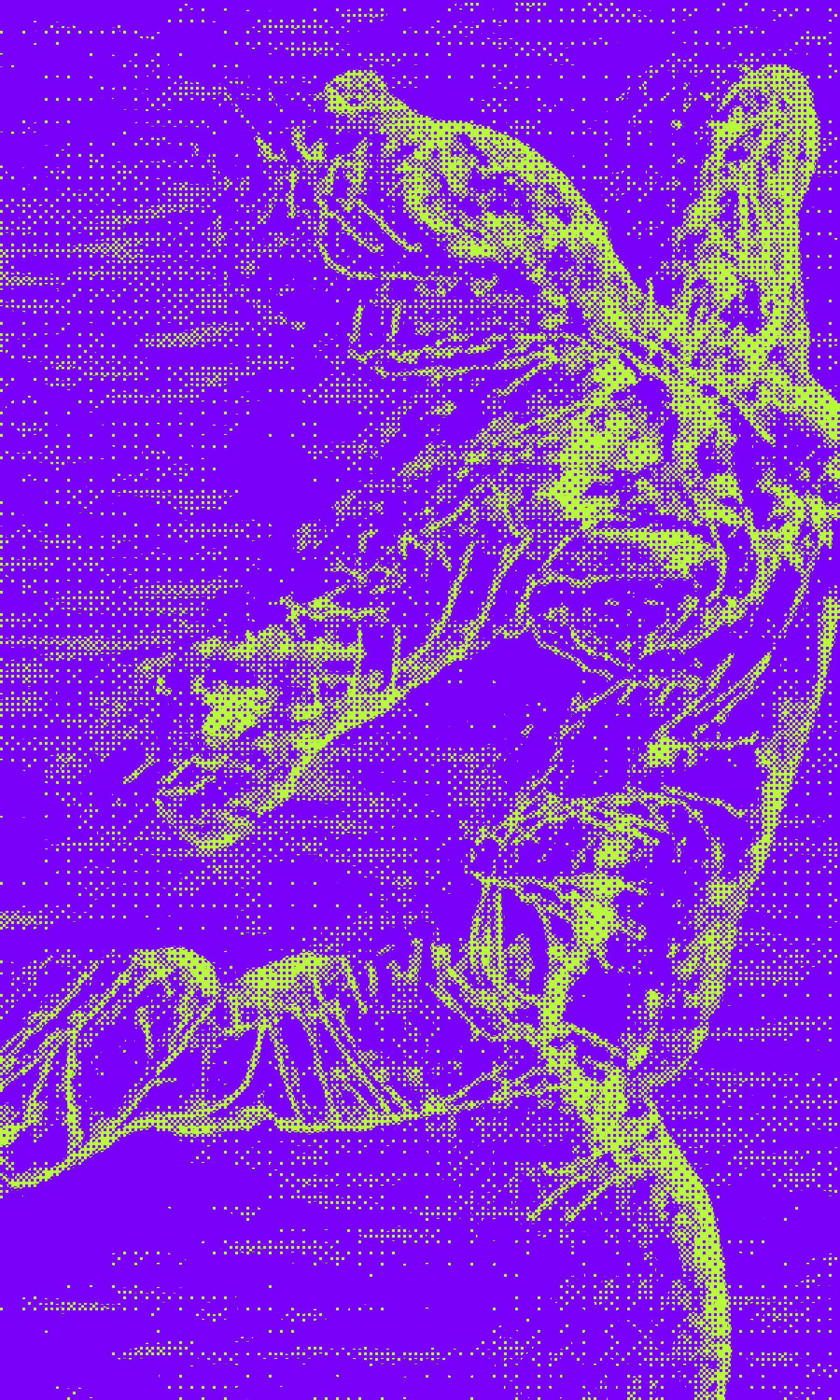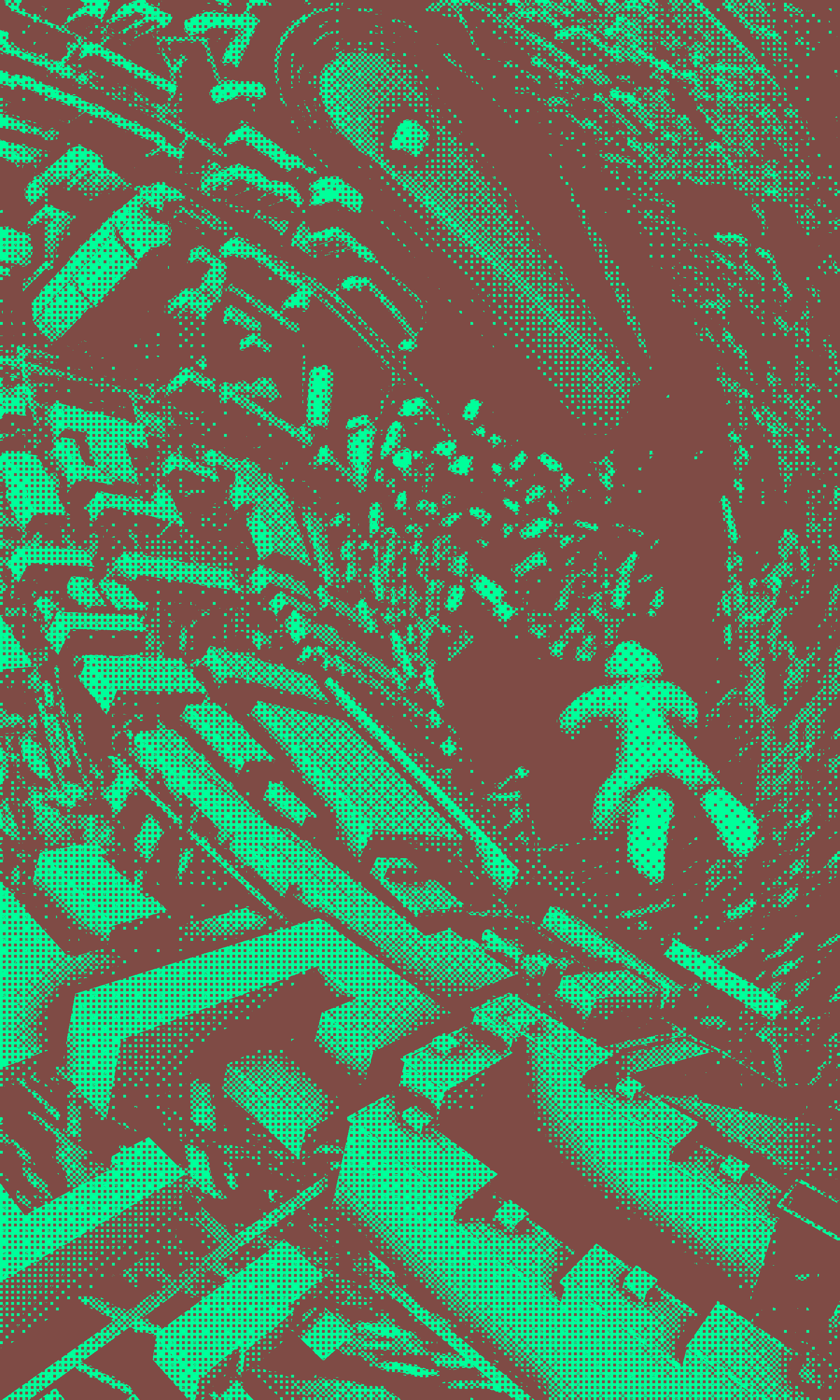ニューアイデンティティ

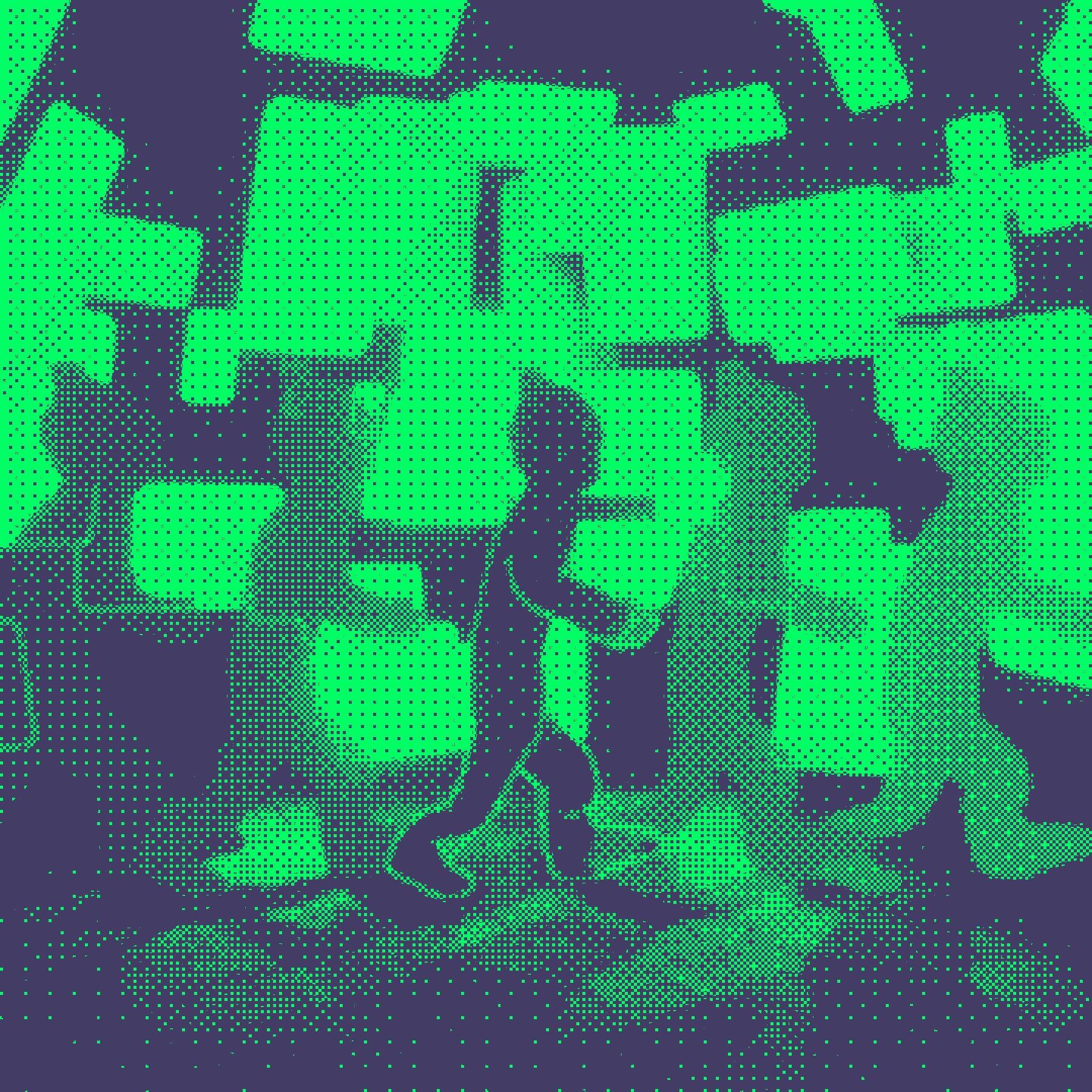
ナンバー
04
アートはいかにして「社会の言葉」を話すのか?
アートは美術館にある嗜好品ではなく、「いま」自分たちがどんな世界に生きているかを知るための“メッセージ”だ。アーティストが生み出すジャーナリズムについて、アルスエレクトロニカの小川秀明に聞く。
2021.05.20
/ Posted on
2021.05.20
- / 聞き手:
- 森 旭彦
- / グラフィック:
- 早川 翔人
この数年間、この世界は「正気」を保つのが難しい出来事ばかりだった。
それは社会に生きる市民に「考える道具」を配る、ジャーナリズムの危機だったとも言い換えられる。
トランプ前米大統領は伝統あるジャーナリズムを「フェイクニュース」と喝破した。しかしコーネル大学の研究者らが3,800万ものCOVID-19に関連した記事を分析したところ、最も影響力のある“フェイクニュース・スプレッダー”はトランプ前米大統領だった。
そして、トランプ前大統領の当選前夜には、膨大な数のトランプ支持のウェブサイトが営利目的のためだけにフェイクニュースをばらまいた。それらのウェブサイトはアメリカから遠く離れたマケドニアの田舎町にすら数多く存在し、そのプロモーションを後押ししたのは、ぼくたちが日常で何気なく使っているフェイスブックだった。パンデミックにおいて、フェイクニュースは実際に人を殺した。アメリカのケーブルテレビ番組を比較調査したシカゴ大学の研究者らの報告によれば、新型コロナウイルスを軽視する内容が含まれる番組を視聴する人が多い地域では、患者数や死亡者数も増加していたという。

こんな時代において、ぼくたちはどのように正気を保ち、的確な判断を下して行動することができるだろうか?
今回はこのジャーナリズムの難問に、アートからの選択肢を提示する。オーストリアにある文化施設「アルスエレクトロニカ」のフューチャーラボで共同代表を務める小川秀明が探求する「アーティスティックジャーナリズム」について聞いた。
(im)possible baby
ここから少し先の未来。ある幼い少女は自分が女性であることを知った。
知った、というよりも、自分の知る世界には身体の特徴が自分と同じ女性と、異なる男性という存在がいることを理解できる年齢に達した、そんな少女を想像してほしい。
その日はその少女にとって特別な日だった。なぜなら、その少女の父親と母親は、周囲の友人らの両親と異なり、両者とも自分と同じ性別、すなわち女性だったからだーー。
この未来は、ひとりのアーティストが描いたものだ。絵の具で描いたのではない。サイエンスの知識で描いてみせたのだ。
アーティスト・長谷川愛による《(im)possible baby》、「(不)可能な子ども」と名づけられたこの作品は、実在する同性カップルの遺伝情報から、生まれるであろう子どもの容姿や性格等を予測し、CGで描いた。そして架空の家族写真として提示したものだ。
驚くべきはそのディテールだ。眼球の中で光の入る量を調整する働きをする「虹彩」は、ひとそれぞれにユニークな形をしているが、遺伝情報によって理論的な予測が可能だという。この予測を実現する情報が、ぼくたちをいま、ある「かたち」にしている、DNAの塩基配列の微細な違い「SNPs(スニップス)」だ。彼女のウェブサイトにはどのようにして理論的に形態を復元したかの詳細な説明がある。
長谷川がこの作品で生み出したのは、サイエンス的に起こりえる未来である「同性間での子どもの誕生」に関する議論だ。
「アルスエレクトロニカでは、アートをいわゆる“装飾”のようには捉えません。わたしたちはアートが生み出す新たな対話に着目し、これを新しい形のジャーナリズム《アーティスティックジャーナリズム》として提示することを試みています。近年、アルスエレクトロニカ・フェスティバルに参加するアーティストたちが作品説明をするときに、アーティスティックジャーナリズムという言葉を使うようになったからです」(小川秀明)
アルスエレクトロニカはオーストリア、リンツにある文化機関で、1979年以降40年にわたってメディアアートの世界的祭典「アルスエレクトロニカ・フェスティバル」を開催している。同祭典のコンペティション「プリ・アルスエレクトロニカ」から生み出されたサイエンス、テクノロジーの未来は数多く、「Wikipedia」(2004)も、かつてはグランプリ「ゴールデン・ニカ」に表彰された“アート作品”だった。長谷川愛の《(im)possible baby》も、2016年のフェスティバル「RADICAL ATOMS」で展示されている。
アートはいかにサイエンスを物語るのか
小川は昨年、アーティスティックジャーナリズムに関する連続講義を慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)で行い、WIRED日本版編集長の松島倫明らと対話を重ねている。その中で小川は、アーティスティックジャーナリズムがサイエンスジャーナリズムに果たす役割に着目している。
サイエンスジャーナリズムは新たな自由を希求し続けている、ジャーナリズムのジャンルだ。というのも、このパンデミックから分かるように、現代においてサイエンスは物事を判断する上で重要な知識だ。それに、先鋭的なバイオテクノロジーやAIなどは、過度にこの社会を変化させてしまう可能性があるため、適切な議論が社会で醸成されていなければ適合不全を起こし、モラルハザードになりかねない。
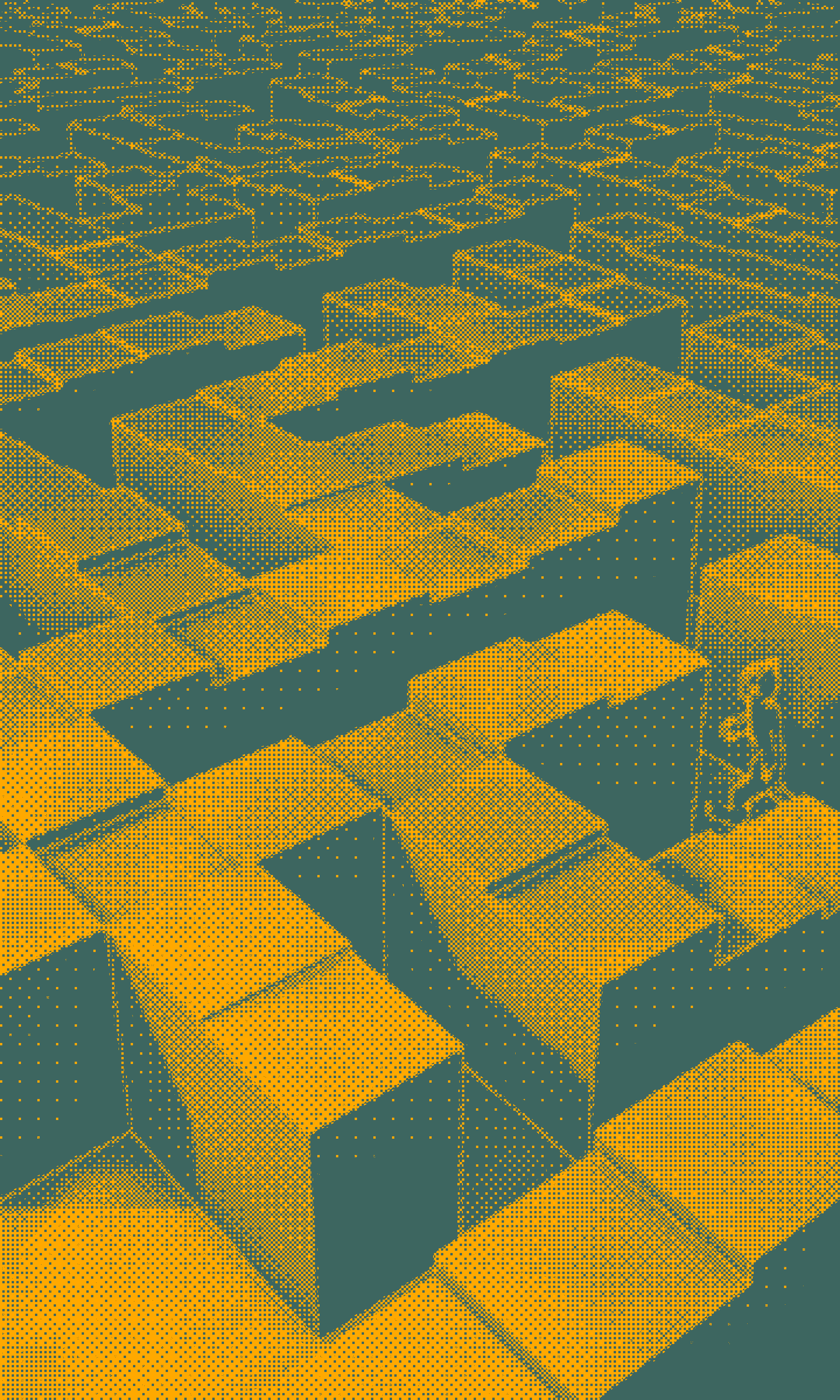
しかし、一般的なジャーナリズムにおいて用いられるメディア(webや新聞)では、サイエンスニュースは伝わりにくく、多くのリーダーを獲得できないものだ。サイエンスジャーナリズムにより効果的なストーリーテリングを求めるジャーナリスト、メディア関係者、研究機関は多い。アーティスティックジャーナリズムは、こうしたサイエンスジャーナリズムの潜在的な課題を解決する可能性があると小川は話す。
「サイエンスは知識をつくり、アートは対話をつくる」と、小川は《サイエンスとアーティスティックジャーナリズム》についての回で話していた。
「サイエンティフィック・リサーチと、アーティスティック・リサーチはとてもよく似ている。しかしサイエンティフィック・リサーチが、結果を論文としてまとめ、サイエンスコミュニティに還元する一方で、アーティスティック・リサーチは、結果をアート作品として制作・展示することでオーディエンスとの対話をつくる。バイオアーティストなどにはサイエンスをバックグラウンドを持つ者も多く、実際にサイエンスを実践しながら制作を行うことも多い」(小川)
とくにメディアアーティストと呼ばれるアーティストがそうだが、作品の制作そのものが、何らかのリサーチになっていることが多い。それが作品の強度をつくるからだ。リサーチのアウトプットが論文とは異なるが、アーティストはサイエンティストと非常に近いことをやっているのだ。
では、アーティストはどのようにして対話を生み出すのか。小川は、オーストラリアのビジュアルアーティスト、パトリシア・ピッチニーニの彫刻作品「The Listener」を紹介した。この作品は、シリコンや人毛などを用いて丁寧につくられた、豚と人間の中間のようなかわいらしい「ヒューマノイド」だ。もちろん、生きてはいない。動かない彫刻作品だ。しかしこのヒューマノイドは進歩し続ける合成生物学の延長上に存在する未来を暗示しており、人間が自然を改造することの是非を見る側に問いかける。これがアーティストのつくる対話なのだ。
「言い方を変えれば、科学者が《scientific question》をつくりだす一方で、アーティストは《social question》をつくるということ。アーティストはサイエンスの専門知を翻訳し、社会において対話する場をつくるエージェントとも言い換えられる」(小川)
小川のアーティスティックジャーナリズムの講義は、オンライン講義の最先端を行くものだった。アルスエレクトロニカセンターにある展示をインタラクティブなビデオ中継で見ることができたり、国内外のゲストを呼んで開催されるトークも充実していた。皮肉にもパンデミックを機に定着した、時間と場所の制約を受けないオンライン講義は、アカデミアの知の継承をより充実させるだろう。
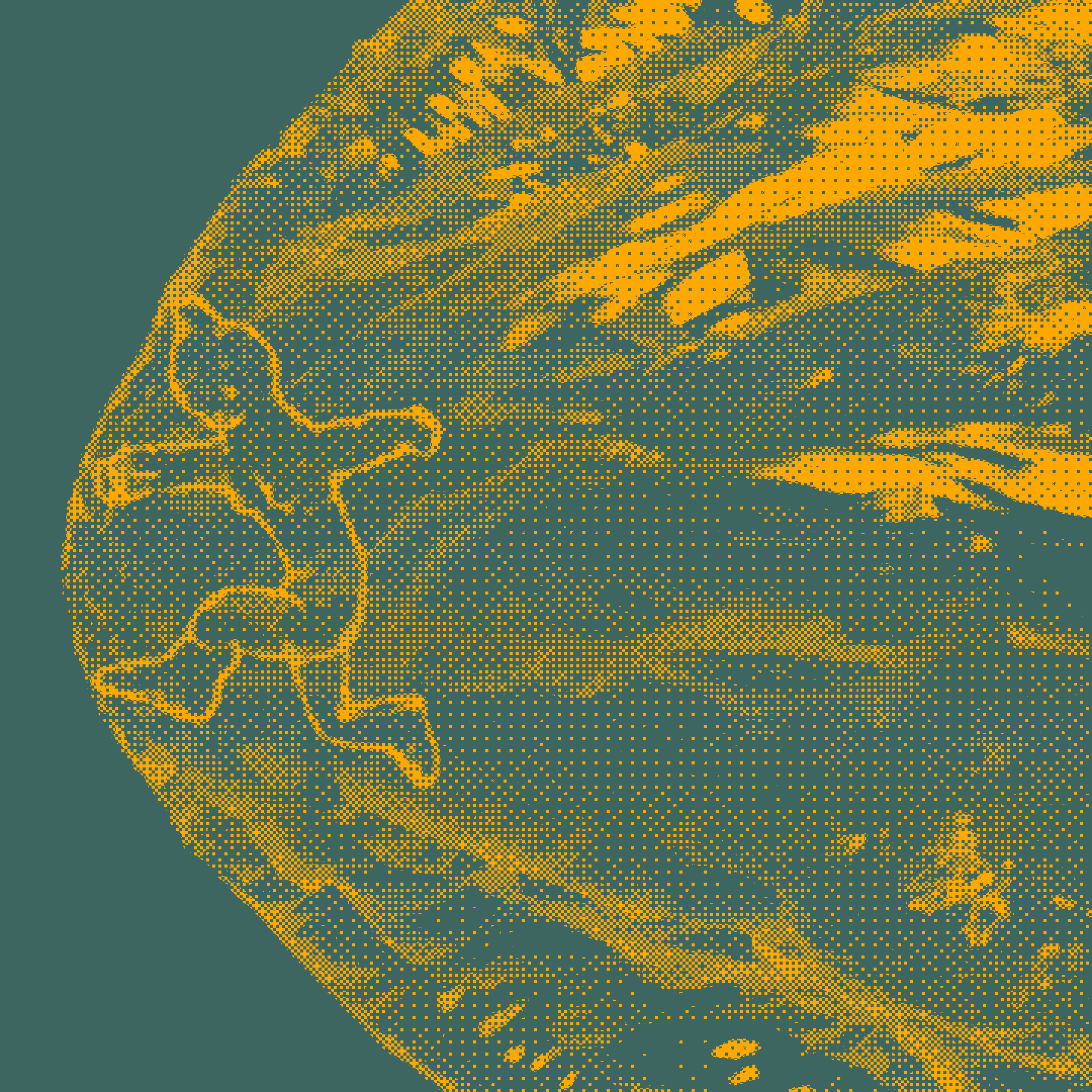
想像力がジャーナリズムを自由にする未来
現在、ジャーナリズムにおいて大きな課題となっているのは、長期的な社会課題をどのように市民に伝え、行動変容を促すかということだ。
イギリスで約10年にわたって調査報道に特化しているマガジン《ディレイド・グラティフィケーション》の報道(issue #38, 2020年刊行)によれば、「世界経済フォーラム」は2007年以降年次で世界規模の危機をリスト化し、提示しているが、パンデミックが危機として挙げられたのは、リストされた危機の総数170のうち、たったの2回だ。この数はデータ漏洩や石油価格の高騰といった危機を下回る。リストは政策立案者や有識者の見解からまとめられているものだが、長期的視野に立ち、来る危機に備えるのは非常に難しい。そして市民に注意喚起し、行動の変容を促すことはさらに難しく、ジャーナリズムの課題と言える。
こうしたジャーナリズムの課題にこそ、アーティストが関わる余白はあるのかもしれない。それに、「正気」を保つのが難しい時代において、ジャーナリズムがその自由を、アーティスティックな想像力に求めるということは、必然とも考えられる。
アートが社会の「言葉」になるとき、ぼくたちは今よりもう少しだけ、思慮深くなり、豊かに生きているのかもしれない。
小川秀明 アルスエレクトロニカ・フューチャーラボ共同代表
2007年よりオーストリアの文化機関「アルスエレクトロニカ」でアーティスト、キュレーター、リサーチャーとして活動している。